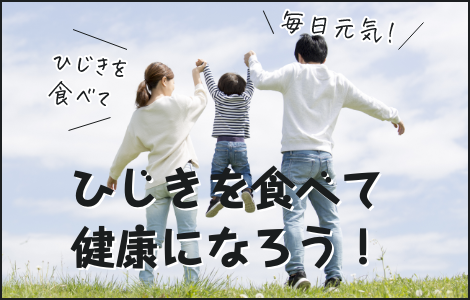協議会について
日本ひじき協議会は日本に古くから 健康食として親しまれてきた食品である“ひじき”を国民的な健康食として もっと情報を発信し日本人の健康増進に貢献を目的として発足。
業界では1980年代にひじきのメニューの提案・健康食としてのアピールを図るため、 ひじき祭り実行委員会を発足しひじきの無料配布・食べ方の提案・アンケート調査などを 三重県の加工業者を中心に活動をして参りましたが、 今般全国的に展開を図り、より国民的健康食としてのアピールをすることにより 健康増進に貢献でき、全国の製造メーカーのレベルのアップと 企業間の情報の共有化とひじき業界の 健全な発展をめざし2004年度に現在の日本ひじき協議会が発足しました。
業界では1980年代にひじきのメニューの提案・健康食としてのアピールを図るため、 ひじき祭り実行委員会を発足しひじきの無料配布・食べ方の提案・アンケート調査などを 三重県の加工業者を中心に活動をして参りましたが、 今般全国的に展開を図り、より国民的健康食としてのアピールをすることにより 健康増進に貢献でき、全国の製造メーカーのレベルのアップと 企業間の情報の共有化とひじき業界の 健全な発展をめざし2004年度に現在の日本ひじき協議会が発足しました。






ひじきレシピ紹介